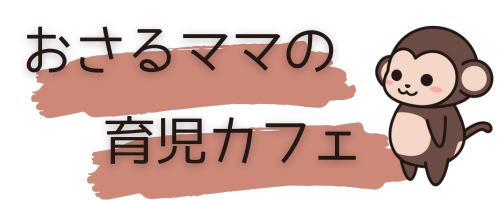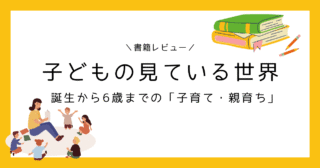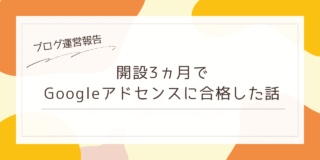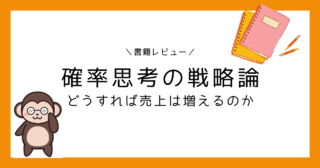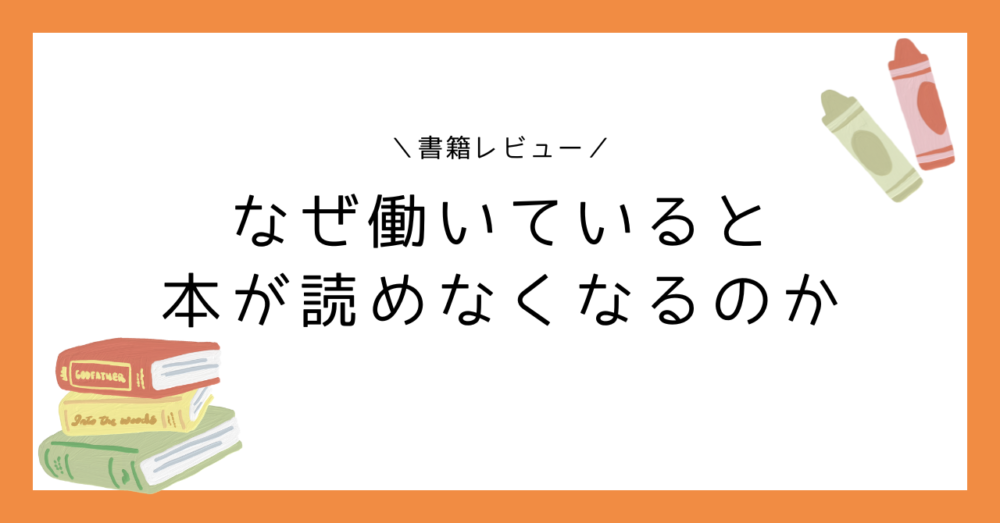
最近読んだおすすめ書籍の紹介です。仕事や家事育児など、働きすぎてお疲れの方にぜひ読んで欲しい一冊です。考え方が変わるきっかけになるかもしれません。
著者:三宅香帆
出版社:集英社
出版年:2024年4月17日
ページ数:230ページ
この本を手にとったきっかけ
令和ロマンの「令和ロマンの娯楽がたり」という特番に著者が出演していて、この本を紹介していたことがきっかけでした。
(「令和ロマンの娯楽がたり」は色んな娯楽を分析していて、トーク番組好きの私としてはとても面白かったです。良かったら見てみてください。)
本のタイトル「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」に共感したため、読んでみたいと思ってkindleで即買いしました。
本の要旨
本のタイトルでは“読書”をテーマにしているように見えますがそうではなく、“働いていると本が読めない”=“働いていると文化的な活動の時間がとれない”という趣旨をテーマにしたものになります。
明治以降の読書史と労働史を用いて、現代日本の働き方について提言しています。
労働と読書との関係の変化
労働と読書との関係の変化について著者はこのようにまとめています。
社会で成功するために必要なのは「社会に関する知識(教養・勉強)」
→必要な知識を得るために読書する
社会で成功するために必要なのは「その場で自分に必要な情報を得ること」
→自分に関係のない知識はノイズ。本にはノイズが多い
つまり、現代では自分に必要な情報をすばやく得る必要があるため、情報取得のツールは本に限ったことではなくなりました。
社会における読書の位置づけは「知識の取得」から「ノイズを楽しむもの」に変化していると指摘しています。
日本人の働き方
日本人の働き方についても指摘しています。
日本人は全身全霊で働くことを美徳とし、非効率な長時間労働を抱えて生きているから「仕事以外の文脈を取り入れる余裕のない」社会を作っていると述べています。
著者の提言する“本が読める社会”
新時代の働き方として「半身社会」を提案しています。
全身全霊のコミットメントはいつか社会の均衡を崩すとして、仕事も家事も部活も趣味もあらゆる物事に対して「半身」でコミットメントすることが「働きながら本を読める社会」につながると述べています。
読んだ感想
ゆっくり本を読む余裕がない現代社会に対する不満は非常に共感するものでした。と同時に「半身社会」を作るという思考も共感しました。
具体的な方法までは言及していませんが、この本の考え方は多くの人を救済することができるのではと思います。みんなで“がんばりすぎない社会を作る”ことで、多様性のある持続可能な社会を作る。良いこと尽くしではないでしょうか。
頑張りすぎてお疲れの方や、自信をなくしかけている方にぜひ読んでほしい本です。