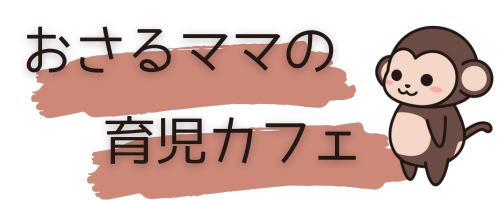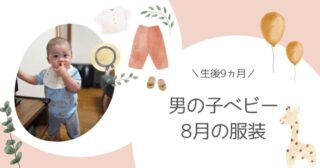‐前編‐-1.png)
こんにちは、おさるママです。
私の息子は現在生後1ヵ月の時に「鼠経ヘルニア」と診断されました。
当時はその診断にとても焦りましたが、医師の指導に従い落ち着いた生活をしています。
「鼠経ヘルニア」は生まれつきみられる症状のようで、あまり珍しいことでもないようです。
今回は「鼠経ヘルニア」と診断されてから治療までの道のりについてまとめたいと思います。どなたかの参考になれば幸いです。
本記事は前編・後編の2部作となります。
前編では1ヵ月検診での診断から手術が決まるまでの経緯についてまとめています。
後編は別記事としてアップしますので更新までお待ちいただけますと幸いです。
- 1ヵ月検診の様子について知りたい人
- 鼠径ヘルニアについて知りたい人
- 赤ちゃんの病気について知っておきたい人

まさか自分の子が手術をすることになるなんて…!いつも元気なのにこんなことあるんだ…って思ったよ。
今は落ち着いて日々を過ごせているよ。
それでは本編です。
1ヵ月検診の様子
息子は1ヵ月検診の時に要精密検査の診断をもらいました。
1ヵ月検診は私と夫そして息子の3人で行きましたが、診断をされた時は私も夫もとても動揺したことを覚えています。
それではまず、1ヵ月検診の様子についてお伝えします。
1ヵ月検診の流れ
1ヵ月検診は出産した産院でみてもらいました。
ママの産後の状態チェックと赤ちゃんの発育チェックが主な内容です。
当日の流れはこのような感じでした。
妊婦検診の時と同じように血圧と体重を測り、採尿をしました。
赤ちゃんの身長・体重を測り、K2シロップを飲ませてもらいます。
産婦人科医による診察があり、子宮の状態や会陰切開の傷痕を確認します。
小児科医による診察があり、赤ちゃんの発育状態を確認します。育児に関する相談もできます。
問題を指摘されたのは小児科医による赤ちゃんの診察の時でした。
小児科医からの思わぬ一言
小児科医による診察の際に思わぬ一言がありました。
「あっ…お母さんこれ気付いてました?」
よーく見ると、鼠径部(足のつけ根)の大きさが左右違っていました。左側だけモコっと膨れていました。
私は言われるまで気付いておらず、赤ちゃんってそういうものなのかな?程度に思っていました。
そして小児科医から追加で一言
「これ…手術が必要ですね」
「えええええ…!!」と私も夫もびっくりして頭が真っ白になりかけました。順調そうに育っていた息子がまさかの手術とは。
その後は淡々と状況の説明があり、詳しい診断は大学病院に行ってくださいとのことでその日は紹介状をもらって帰りました。
大学病院での診察
翌日には大学病院の予約をとり、診察を受けることにしました。
診療科は「小児外科」です。
診断結果
大学病院ではエコーによる診察を行ってもらいました。
診断結果は「鼠経ヘルニア」でした。
赤ちゃんの場合、胎児期の成長の過程で生まれつき発症することが多いようです。
鼠経ヘルニアとは?
「鼠経ヘルニア」について知らない方も多いかと思います。
日本小児泌尿器科学会のHPを参考にどのような症状なのかお伝えします。
小児の鼠経ヘルニア 日本小児泌尿器科学会鼠径ヘルニアは、一般には脱腸(だっちょう)と呼ばれています。股の付け根の少し上あたり(鼠径部)から陰部にかけて膨隆する疾患です。(中略)女児に比べて男児に多いとされます。
女の子より男の子が発症する割合が多いようで、発症確率は30人に1人くらいだそうです。クラスに1人いる程度と考えると結構多く感じます。
鼠経ヘルニアは成長の過程で自然と起こってしまった脱腸状態を言います。
ごくまれに脱腸した腸が詰まってしまう「嵌頓(かんとん)」という状態に陥ることがあるようで、痛み・嘔吐・腸の腐敗が起こるため、これに注意しなければならないと医師から告げられました。
息子の鼠径部が片側だけモコっと膨れていたのは脱腸していたからだったことが分かりました。
治療方針
鼠経ヘルニアは成長の過程で自然と治ることもあるようなので、医師と相談しこのような治療方針を立てました。
また、当分の間の対処療法についても教えてもらいました。
- 生後6ヵ月頃を目安に手術をするかどうか決める
- 月に1回通院して経過をみる
- 腹圧をかけないため、毎日浣腸をして定期的にウンチを出す
- 脱腸していたら指圧で元に戻してあげる
手術の目安は身体が麻酔に耐えられる生後10か月頃とのことで、スケジュール調整のために生後6ヵ月頃に手術をするかどうか決めることにしました。
それまでの対処療法としては腹圧をかけると脱腸してしまうため、腹圧をかけすぎないための浣腸を毎日することと、脱腸していたら手で戻してあげるやり方を教えてもらいました。
そして、月に1回大学病院に行き経過観察を行うことになりました。
お家での過ごし方
診察以降は医師からのアドバイスの通り、
- 日に1~2回浣腸をすること
- 脱腸をしていたら手で戻すこと
を意識して過ごしました。
やってみての感想ですが、毎日浣腸をすることによってウンチを出すタイミングをコントロールできるため思いの外良かったです。
外出先で思わぬウンチが出た!といったハプニングとは無縁の生活になりました。
浣腸に慣れると自分でウンチを出せなくなるのでないか?という心配もありましたが、自分で出すこともできたので問題なかったです。

ウンチ出すとスッキリしてよく寝てくれるからそれも良かったよ
脱腸を戻る作業は正直難しかったです。
医師は簡単にギュギュっと戻していたのですが、何度説明を聞いても上手く戻すことができませんでした。
出た腸を押し込もうとするとギュギュっと音がするのですが、なんだか申し訳なくて力を入れることが出来ず上手く入りませんでした。
-320x421.jpg)
泣いて腹圧がかかるとすぐ脱腸しちゃうんだよね。。でも落ち着くと元に戻るから落ち着くのを待つようになったよ。
手術の決定から検査まで
生後6ヵ月になり状況は変わらなかったため、医師と相談して手術を行うことに決めました。
夫とも「早く手術してヘルニアの心配から解放されたいよね」と話していたので手術が決まって良かったです。
術式について
手術の方法は2つあり、
- 開腹手術
- 腹腔鏡手術
のどちらかになるとのことでした。
傷口が目立たないということで腹腔鏡手術で行うことにしました。
入院期間は2泊3日になるとのことでした。
事前の検査
手術が決まると手術を行っても問題がないかどうかの事前検査がありました。
1時間くらいで3つの検査を行いました。
- 血液検査
- レントゲン
- 心電図
検査は生後9ヵ月になってから行いましたが、小さい身体で慣れない検査を行っている様子を見て胸がキュッとなる感覚がありました。

血液検査の注射でギャン泣き…レントゲン台の上でギャン泣きして可哀想になったよ…。
よく頑張ったねーって終わるたびに抱きしめたよ。
検査の結果はその日に分かるわけではなく、手術当日のデータとなるようでした。
おわりに
今回は息子が鼠経ヘルニアと診断されるまでの経緯や手術が決まるまでの様子についてまとめました。
まさかいつも元気に過ごしていた息子が手術になるとは思ってもみなかったため当初は焦りましたが、今は落ち着いて日々を過ごしています。
後編では実際に手術をしてからその後の経過までをまとめたいと思います。
2泊3日の入院はどうやって過ごすのか、手術は無事済むのかドキドキです。
続編はこちらからご覧ください。
ここまでご覧いただきありがとうございました。