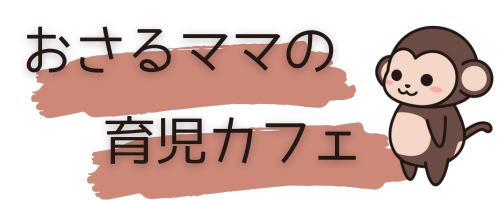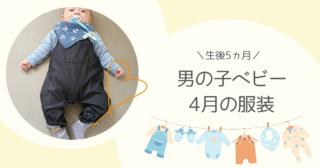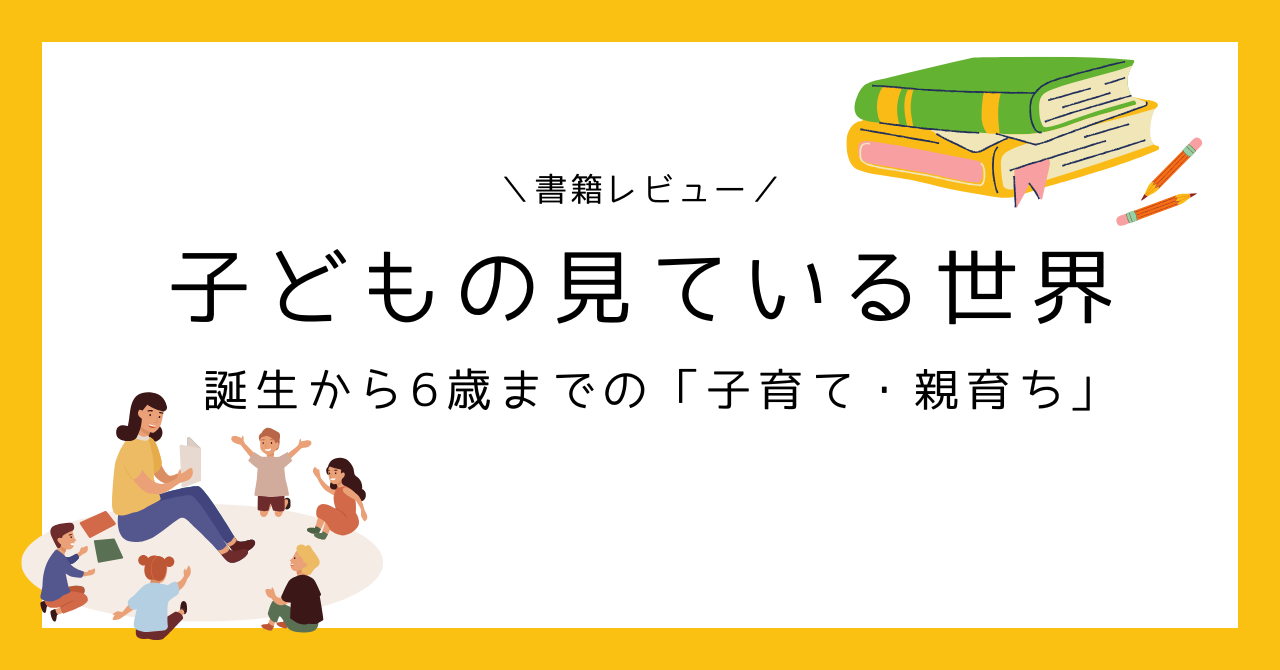
最近読んだおすすめ書籍の紹介です。育児や保育に携わる人にぜひ読んでもらいたい一冊です。
著者:内田伸子
出版社:春秋社
発売日:2017年5月23日
ページ数:232ページ
この本を手にとったきっかけ
子供が産まれて、幼児教育について考えている時に出会いました。幼児教育について考えるきっかけは母親からの一言でした。
「将来、●●君をインターナショナルスクールとか入れるの?」
正直、どんな学校にいれたいかまでは考えてなかったのですが、(子供はまだ0歳なので。笑)“子供にとって良い教育とは?”“子供の英語教育ってどのくらい重要?”と考えるきっかけになりました。そこで、幼児教育について研究している専門家を調べている時に、著者の内田伸子さんを知りました。
お茶の水女子大学名誉教授。
発達心理学・認知心理学・発達心理言語学・保育学を専門とする。
児童書や「こどもちゃれんじ」など監修多数。NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」の番組開発、おもちゃ開発などの実績がある。
You Tubeチャンネル「News picks」にも出演されていて、早期英語教育についての見解について説明していましたが、もっと深くこの方の知見を知りたいなと思い、本を購入しました。
News picksの動画はこちら
この本を読んでわかること
この本を読んでわかる主な事柄をまとめてみました。
子供の不思議な言動の意味
大人から見ると不思議に見える子供の言動の意味についてわかります。例えば、
- 赤ちゃんはなぜ泣くか
- 2歳児のイヤイヤのもつ意味
- 3歳児のひとりごとの意味
などといった言動です。大人から見ると不思議で困った言動のように見えても、成長過程で必要だということが分かると子供への理解が深まると感じました。
発達の性差について
“一般的に女の子の方が成長が早い”と言われたりしますが、その理由について脳の構造上の理由を用いて説明しています。男の子の方が成長が遅くなるのは生物学的な理由があることがわかり興味深いです。医学的な専門用語が出ることもありますが、とても分かりやすく説明しています。
各年齢ごとの認知機能の発達について
各年齢ごとに見られる認知機能(言語能力や行動的な能力)について分かりやすく説明しています。例えば下記のような内容です。
- 物事のルールが分かる年齢は?
- 人格の土台形成がされる年齢は?
- 人生の充実に大きく影響を与える年齢は?
- ことばの発達はいつから始まる?
知識として知っておくと年齢に応じた適切な子供との向き合い方がわかるため、世のママさんパパさん必見の内容だと感じました。
映像メディアとの付き合い方
テレビや教育用映像メディアとの付き合い方について説明しています。例えば、以下のような内容です。
- 子供は映像の内容をどこまで理解できるのか
- 早期教育用映像を見せすぎると起こる弊害
- 映像メディアとの上手い付き合い方
テレビやYou tubeなどの映像メディアが発達している現代だからこそ、気を付けたい内容が書いてありました。映像メディアの危険性だけでなく、上手い付き合い方についても書いてあるのでぜひ取り入れていきたいです。
子供の早期英語教育の是非について
この本を読むきっかけとなったテーマになります。
- 早期英語教育をすることの影響
- 適切な外国語習得のタイミングや方法
このような内容について説明しています。結論が明確で分かりやすく、英語教育を考えるタイミングになったら取り入れていきたい考え方だなと感じました。
学力格差について
幼児教育と、就学後の学力との関係について説明しています。
- 学力と親の経済力の関係
- 学力と習い事の関係
- 保育園と幼稚園どちらが学力が高くなるか
- 学力としつけ方の関係
このような内容について説明しています。結論が明確で分かりやすく、家庭内での接し方や将来の学習環境を考える時の参考にしたいと思いました。
この本からの学び
子供との向き合い方や子供に提供したい環境についての気づきになりました。例えば、
- 自我が芽生えた時は子供の意見を尊重した上で、しつけを行うべき時はきちんとしつける
- 体験からの学びが大事。テレビやおもちゃに頼るのではなく、自分で自由にやってみる体験が成長を促す
- 外国語習得についてはまず母国語の習得を優先する。発音よりも発言の中身の方が大事
- 語彙力などの認知機能向上のためにいろんな人や本と触れ合うことが大切。そういった環境を用意することが親の役目
- 子供が自ら気付き・考え・表現することが大事。そのために親は待つ・見守る・急がない・急がせないを心がける
このような気付きを得ることができました。
この本は筆者の意見だけでなく、フィールド調査をもとにした学術的な見地からの内容が盛り込まれているため、とても論理的で説得力の高い内容となっています。頻繁に読み直したい本だなと感じました。
こんな人におすすめ
子供と関わる、これから関わる全ての人におすすめです。例えば、
- 保育士さんや幼稚園・小学校教員など、子供の教育に携わる人
- 子供を育てているお父さんお母さん
- これから子供を持ちたいと考えている人
ぜひ読んでいただきたい一冊です。