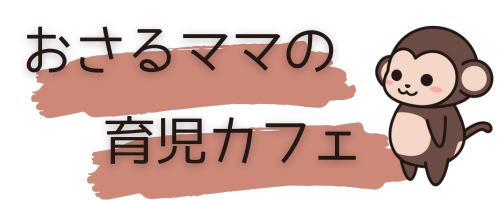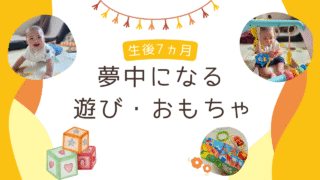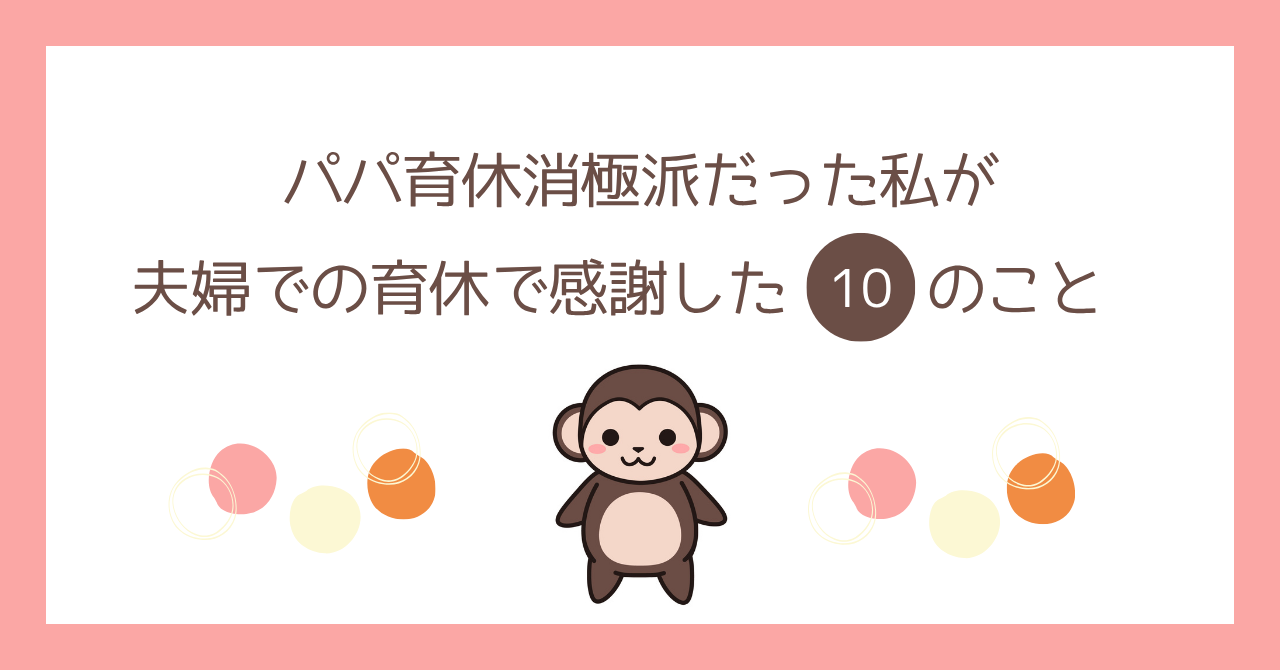
我が家では夫が半年の育休を取得し、夫婦で協力して育児を行いました。
夫の育休期間が終了したため、良い機会なので育休期間を振り返ってみたいと思います。
- これから夫婦で育休を取得するママさん・パパさん
- 夫の育休取得に前向きになれないママさん
- 育休を取得するか悩み中のパパさん
実は私は夫の育休取得について前向きではありませんでした。
「お父さんってまずは仕事を全力でするものでしょ?」って思い込みが心のどこかにあったのだと思います。
我が家は夫の強い意志があり育休を取得したというレアケース(?)です。
今回は夫婦で育休期間を過ごして気付いた点について包み隠さずお伝えしようと思います。
まず結論から言ってしまうと、夫婦で育休を取得することが出来て本当に良かったです。かけがえのない時間を過ごすことができました。
具体的にどんな点が良かったのか、夫婦での過ごし方や事前に決めたルールについてお伝えします。
夫婦育休中の過ごし方については下記記事でも紹介しています。宜しければこちらもご覧ください。
それでは本編です。
パパ育休に前向きになれなかった理由
私の妊娠が分かった後、夫から育休についてこのように告げられました。
「長めに育休取ろうと思う。今しかできないことだし。最低でも半年、長くて1年取ろうかな。」
この話があった時、正直、、内心ゾッとしました。決して夫が嫌いとかそういうことではないです。夫婦仲は良好です。
あまり前向きになりきれなかった理由はこんな感じです。
- 家事負担が私の方が重い(と感じていた)
- 私自身一人時間が必要なタイプで、一人時間が奪われると思った
- 収入減が気になった
家事分担については主に料理についてです。夫は全くと言って良い程料理ができません。「朝昼晩毎日私が料理するのか…」と憂鬱になりました。
料理って一言で言っても工程が多いと思うのです。レシピを考え、下ごしらえをし、調理し、盛り付け、食器の片づけ…すべて自分で行うととてもエネルギーを使います。夫から「適当で良いよ」と言われても本当に適当にするわけにもいかず、無理をしてしまいます。
夫にはこのモヤモヤを正直に打ち明けました。今思うと結構強めに詰めてしまった気がします。
-320x421.jpg)
育休1年って…その間何するの?

えっ…育児。。。
-320x421.jpg)
…それだけ?大人一人家で過ごすだけでどれだけ家事が増えるか分かる?

もちろん家のこともやるよ。息子とママのサポートするための育休だし。
夫婦で育休を取得するにあたり決めたこと
私が抱いていた不安やモヤモヤを解消するため、夫婦育休中の過ごし方について夫とこのような方針を立てました。
- 家事・育児は分担して行う
- 料理については宅食を利用することで妻の負担を軽減
- お互いに一人で外出できる時間を毎日設ける
- 収入減を考慮して夫の育休は半年間にする
このような方針のもと、半年間夫婦二人三脚で育児に取り組みました。
結果、とても良い時間を過ごすことができました。
夫婦での育休で感謝した10のこと
夫婦で育休期間を過ごした結果、思った以上に良い点がたくさんありました。
今となっては育休を取得すると言ってくれた夫には本当に感謝しています。
物理的なメリットと精神的なメリットの両面あったように思います。具体的に夫婦での育休の良いところについて挙げていきたいと思います。
睡眠時間を確保できる
これが一番大きいメリットと思います。
新生児期から生後3ヵ月くらいまでは頻回授乳が続きます。だいたい3時間おきに授乳を行う必要があるため、ワンオペで育児を行うとなると、まともに寝ることが出来ません。
睡眠時間が削られると親の体力の消耗が激しいですし、体調・メンタル両方に良くないです。
我が家では夫が夜間授乳(22:00~3:00)を行ってくれたため、夜はぐっすり眠ることが出来ました。
夜まとまって寝ることで体調・メンタルが回復し、毎日の家事・育児を前向きな気持ちで行うことができます。
起きて朝に見る息子の笑顔が可愛くて仕方なかったです。
一人の時間を作ることができる
毎日最低1時間程度、お互いにフリーで行動できるようにしていました。
家事や育児から一時的に解放されることでリフレッシュすることができます。
フリータイムの過ごし方は日によって様々で、散歩や買い物・ジムなどに行くことが多かったです。
この時間を使って私はカフェでブログを書いたり、美容院に行ったりして自分を取り戻していました。
リフレッシュする時間は大切です。夫と交代で一人時間を確保することが出来て本当に良かったと感じています。
気兼ねなく家事ができる
ワンオペで家事・育児を行おうとすると、子どもの状況次第で手を止めなければならない時が多々あり家事がまともに進まないことがあると思います。
泣き出した…!寝返りした…!となるとどうしても様子を見に行きますよね。
そして溜まった家事を子どもが寝ている間にしようとすると自分の睡眠時間を削ることになるので辛いです。
夫が家にいることで子どもを安心して委ねることができ、家事に没頭することができました。
特に料理の時はすぐにキッチンから離れることが難しい場面もあるため、ずっとキッチンに居られる状況は有難かったです。
平日に外出できる
夫が毎日家にいるため、当然ですが平日外出が可能になります。
休日に比べると空いている所が多いため、ファミレスや回転寿司・ショッピングモールなどを堪能することができました。
また、遠方への帰省も平日に気兼ねなくすることができます。
高速道路やサービスエリアが空いているため、とても快適に移動することができました。
一緒に保活ができる
夫と一緒に保活ができたことも良かったです。具体的には自治体での情報収集や保育園見学です。どちらも平日しか空いていないため、育休中に二人で出来たことはよかったです。
私が住んでいる地域では保育園が激戦になっていることもあり、夫と保育園の入園方針ついて落ち着いて話し合うことができました。
また、夫と一緒に保育園に見学に行くことで、息子に合っていそうな保育園や入園後の生活についてイメージすることができました。「ここの保育園だったら、俺がメインで迎えいくよー」といった会話のイメージです。
新しいことに挑戦できる
仕事から離れ、フリーの時間の確保もできるため、これまで興味があったけどできなかったことに挑戦することができます。
私は育休に入るまで各種SNSは全くやってきませんでした。(そんな余裕すらなかった…)社会との繋がりや、同じ境遇の人とのコミュニケーションを取りたく、ブログやSNSを始めて毎日充実しています。
夫は今後の家族計画や家族レジャーのため、資産運用に本腰を入れ始めました。日々情報収集を行い、資産運用に取り組んでいます。
お互いに仕事のストレスから解放されて気持ちに余裕が生まれる
我が家は正社員共働き夫婦です。
育休に入るまでは仕事の繁忙期などで気持ちに余裕がなくなると、家庭内でもピリピリすることがありました。(特に私…。)
ですが、育休に入って仕事から解放されたことで気持ちに余裕が生まれました。
夫からはよく「子どもを授かってから明るくなったね」と言われます。たしかにそうかもしれません。夫は元から穏やかな性格ですが、より穏やかにそして逞しくなったように思います。
気持ちに余裕が生まれたことでお互いに良い面が引き出されたように感じます。
育児の楽しさ・辛さを共有できる
毎日子どもと接しているからこそ感じる、育児の楽しさや辛さを共有できるのは夫婦での育休ならではの良さだと感じます。
「今日も元気いっぱいだね」「今日寝ないね、、どうしたのかな」といった子どもに関する話がタイムリーにできることで同じ温度感で育児と向き合うことができます。
結果育児を頑張る同志になるため、気付けば心強いパートナーになります。
訪問してくれた助産師さんに「パパがママ友みたいね♪」と言われたのですが、本当その通りだなと感じます。
夫婦でのコミュニケーションが増える
一緒にいる時間が増えるため夫婦でコミュニケーションを取る時間が増えます。
子どもの成長や将来の家族計画のこと、家の購入タイミングや資産形成のことなど、大事な話をじっくりできるのは夫婦での育休期間ならではと思いました。
子どもの成長を二人で見届けることができる
子どもの成長はとても早いです。昨日までできなかったことがあっという間にできるようになったりします。
そんな子どもの成長を夫婦二人で見届けることができるのは夫婦育休の醍醐味です。
「首がすわったねー!」「寝返りができたねー!」といった小さな感動を夫婦で見届けることができ幸せな時間を過ごすことができました。
おわりに
今回は私(妻)目線で振り返る夫婦での育休取得についてまとめました。
育休取得前はどのように過ごすのか不安を抱くこともありましたが、過ぎてみると夫への感謝でいっぱいです。
夫も「人生において幸せな時間だった」と振り返っています。
改めて夫婦での育休取得のメリットをまとめるとこんな感じです。
- 睡眠時間を確保できる
- 一人の時間を作ることができる
- 気兼ねなく家事ができる
- 平日に外出できる
- 一緒に保活ができる
- 新しいことに挑戦できる
- お互いに仕事のストレスから解放されて気持ちに余裕が生まれる
- 育児の楽しさ・辛さを共有できる
- 夫婦でのコミュニケーションが増える
- 子どもの成長を二人で見届けることができる
人生は一度きりです。育休という制度を上手く活用して夫婦でかけがいのない時間を過ごしてみませんか。
この記事をきっかけに夫婦育児を取得し、かけがえのない時間を手に入れるファミリーが少しでも増えたら幸いです。
ここまで読んでいただき、有難うございました。